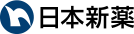 医療関係者向けサイト
医療関係者向けサイト
このサイトで提供している情報は、弊社の日本国内で販売している医療用医薬品等に関する情報を医療関係者(医師・薬剤師・看護師等)の皆様に情報提供することを目的として作成されています。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
日本新薬の医療関係者向けサイトでは、ログイン機能として「medパス」ならびに「Medical Note Expert」の会員システムを採用しております。ログインいただくと、会員向けコンテンツの閲覧および機能のご利用が可能になります。
※medパスのサイトに移動します。
- ※Medical Note Expertのサイトに移動します。
- ※Medical Note Expert会員の場合、一部ご利用いただけない機能がございます。
- 会員限定機能を除いた、本サイトの一部コンテンツ(電子添文などの製品情報)をご利用の方は、対象の職種をお選びください。
- 医師
- 薬剤師
- 看護師
- その他
医療関係者ではない方はこちら
(日本新薬コーポレートサイト)
コンテンツのご紹介
会員限定機能のご紹介
医療関係者の方は、会員限定機能を除いた、本サイトの一部コンテンツをご利用いただけます。
-
製品基本情報

弊社製品の電子添文、
インタビューフォーム、RMPなどの
基本情報をご確認いただけます。 -
Webカンファレンス

弊社製品・疾患に関する
Webカンファレンスをご視聴
いただけます。 -
製品・疾患関連コンテンツ

弊社製品・疾患に関する動画、
html、パンフレットなど様々な形式の
コンテンツをご確認いただけます。 -
使用期限検索

弊社製品名とロット番号から
使用期限をお調べいただけます。 -
よくあるご質問

弊社製品に関するよくあるご質問と
その回答をご確認いただけます。
日本新薬の医療関係者向けサイトでは、ログイン機能として「medパス」ならびに「Medical Note Expert」の会員システムを採用しております。先生のお困りごとを解決できる機能を揃えておりますので、ぜひご登録およびログインをお願いいたします。
こんなお困りごと、ありませんか?

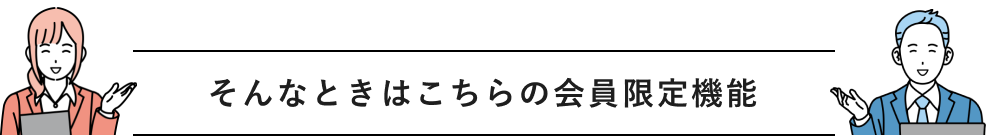
-

メモ機能
先生だけのメモを残せる
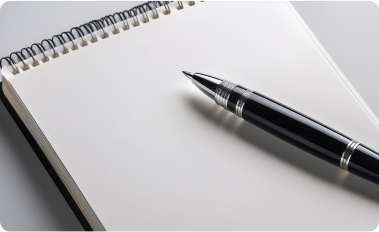
 ◀表示があるページでご利用いただけます。
◀表示があるページでご利用いただけます。 -

お気に入り機能
気になるコンテンツを保存できる
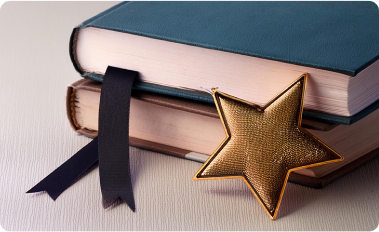
 ◀表示があるページでご利用いただけます。
◀表示があるページでご利用いただけます。 -

クイックアクセス
欲しい情報をおまとめ

-

infoメール
欲しい情報をメールでお届け

-

オンライン廊下※ (チャット)
弊社担当者にチャットでご質問

- ※現在、範囲を限定してトライアル中です。
- ※担当者が対応可能な場合に限ります。
- ※機能のご利用にはmedパスでのログインが必要です。
-

担当MRはこちら
担当MRからのメッセージをお届け

- ※現在、範囲を限定してトライアル中です。
- ※機能のご利用にはmedパスでのログインが必要です。
その他の機能
-
会員限定コンテンツの閲覧

ご診療にお役立ていただける、様々な
会員限定コンテンツをご用意しております。 -
Webカンファレンス

視聴者情報、ID・PWの入力が不要で、
スムーズに視聴いただけます。
見逃し防止のため、リマインドメール、
カレンダー追加機能をご利用いただけます。 -
資材ライブラリー
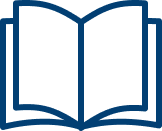
発注履歴をご確認いただけます。
発注者情報の入力が簡便になり、
スムーズにご発注いただけます。
