×
日本新薬 
ご登録いただくと、製品に関するお知らせ、疾患情報、Webカンファレンスや動画コンテンツなどの
新着情報のご案内メールをお送りいたします。
ご希望の製品を選択してください。
肺高血圧症
デュシェンヌ型筋ジストロフィー
難治性てんかん
血液内科領域
鉄欠乏性貧血
泌尿器科領域
アルコール依存症
アレルギー性鼻炎
今後infoメールに追加される新製品の情報の受け取りを希望される場合、以下からご希望を選択ください。
※新製品の情報をご希望の場合は、追加された製品に自動でチェックマークが入ります。
※「po.nippon-shinyaku.co.jp」からのメールを受信許可設定をお願いいたします。
ご登録時の会員情報(お名前、ご所属、メールアドレス等)、本メールへの登録状況を「プライバシーポリシー」に従い安全管理措置を講じたうえで、「個人情報の利用目的」に記載された利用目的ならびに、弊社(MRや弊社サイト等)からの情報提供やサービスのお知らせのために利用させていただく場合がございます。
※本HTMLメールを介した情報「メールを開封/プレビューした日時」、「メール内に記載された各リンクを押下した日時」の取得及び利用についてはこちらをご確認ください。
送信先メールアドレスを変更される場合、
下記から変更をお願いいたします。
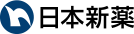
医療関係者向けサイト
このサイトで提供している情報は、弊社の日本国内で販売している医療用医薬品等に関する情報を医療関係者(医師・薬剤師・看護師等)の皆様に情報提供することを目的として作成されています。一般の方への情報提供を目的としたものではありませんのでご了承ください。
医療関係者の方
medパス会員・Medical Note Expert会員として
ログイン
日本新薬の医療関係者向けサイトでは、ログイン機能として「medパス」ならびに「Medical Note Expert」の会員システムを採用しております。会員向けコンテンツをご利用いただく場合は、「medパス」または「Medical Note Expert」のID・パスワードでのログインが必要です。
ログインいただくと、会員向けコンテンツ(一部製品の動画、資材など)の閲覧が可能となり、Webカンファレンス視聴時や資材申込の手続きが簡便にご利用いただけます。
※medパスのサイトに
移動します。
※Medical Note Expertのサイトに移動します。
会員向けコンテンツ以外(添付文書などの製品基本情報)をご利用の方は、対象の職種をお選びください。
医療関係者ではない方