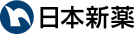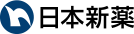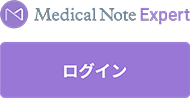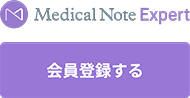移植に携わる
メディカルスタッフの方に
知っていただきたい
造血細胞移植後患者における
肝類洞閉塞症候群(SOS)の管理
- 【監修】
- 岡山大学学術研究院医歯薬学域
血液・腫瘍・呼吸器内科学
准教授 松岡 賢市 先生 - 岡山大学病院 看護部 入院棟3階BCR
看護師長 小倉 妥子 先生
※先生方のご所属・ご役職は、ご執筆当時のものを掲載させていただいております。
現在のご所属・ご役職と異なることがございますが、ご了承ください。
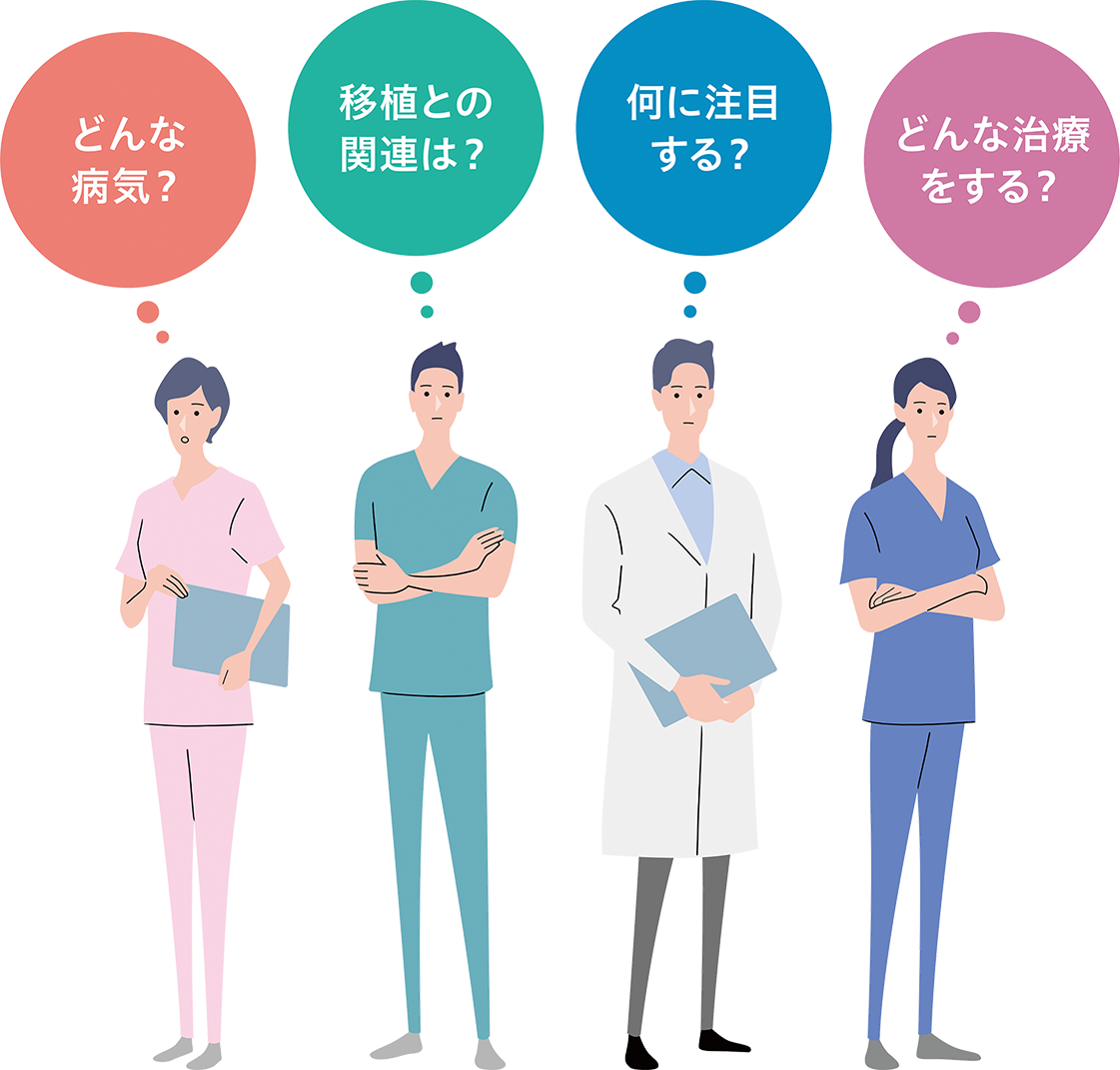
Q&A
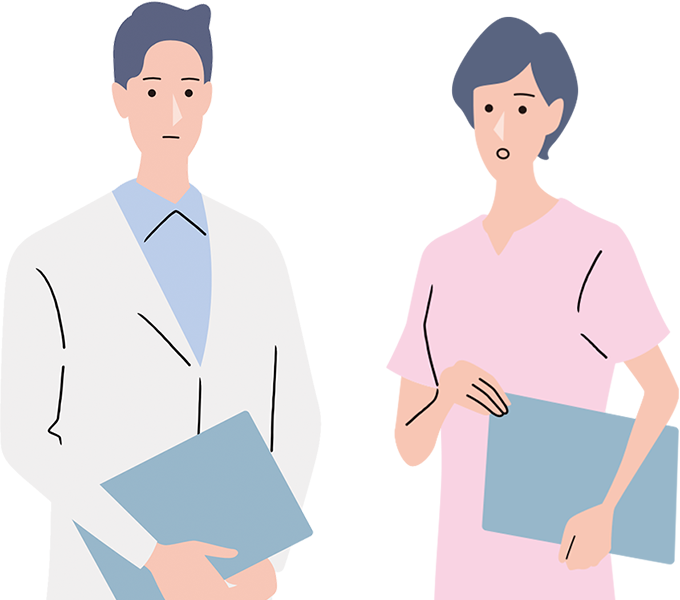
造血細胞移植後患者における肝類洞閉塞症候群(SOS)の管理について、Q&A形式にて解説します。
-
Q1SOSと類縁疾患との鑑別について注意するポイントはありますか?
-
A1
まず肝機能障害という観点では、肝急性GVHD、CMV肝炎、薬剤性肝障害などが鑑別疾患に挙げられます。特に肝急性GVHDに関しては、GVHDそのものがSOSの発症トリガーの1つでもあるため、潜在的に2つの病態が併発している可能性を考慮する必要があります。また、微小血管障害という観点では、TMAの病態機序や発症リスク因子が近いため、同時発症することがあります。
このように移植急性期には、様々な合併症の発症リスクや発症時期が共通しており、明快な鑑別診断が難しい場合が少なくありません。むしろ、これらの病態が重複発症している可能性を常に念頭に置き、臨床的な評価・治療を適時的に行うことが重要と考えています。GVHD:急性移植片対宿主病
(Graft versus host disease)
TMA:血栓性微小血管症
(thrombotic microangiopathy)
-
Q2SOSの発症に関して、移植後いつ頃までモニタリングをするのがよいでしょうか?
-
A2
明確な基準を設定することは難しいですが、移植後100日目までを目途にモニタリングを行うことを1つの基準にしています。ただし、SOS発症のリスク因子を多く有するような、発症の可能性が高い患者さんにおいては、移植後半年程度を目途に、長期的なモニタリングを実施していく必要があります。
-
Q3SOSを管理する上で、移植実施前の時期はどのようなことを意識されていますか?
-
A3
まずはSOSのリスク因子や、診断基準、重症度分類にどのような項目が含まれているかを把握しておき、それぞれを適切なタイミングで評価していく意識が重要です。
他にも、患者さんによってはSOS予防のために投薬が行われる場合もあります。予定通りに内服・投与が行えるよう患者さんに教育を行い、着実に移植を受けられるように努めています。
-
Q4SOSのリスク因子の評価はどのタイミングで行うのがよいでしょうか?
-
A4
移植前処置の内容や、ドナーソースの種類等がSOSの発症リスクに影響を及ぼすことを考慮して、“移植の実施が決まったらすぐ”にリスク評価を行うのが好ましいと考えています。このSOSリスク評価を基に、総合的な移植関連合併症のリスク評価の見直し、前処置・ドナーソースの決定、移植後のSOSモニタリングを強化すべきかの判断などを行っています。
-
Q5重症度分類は、どのタイミングで活用するのが望ましいでしょうか?
-
A5
SOSの診断確定後ではなく、SOSを疑った段階から活用します。患者さんがSOSを発症した後に重症度を判定するだけではなく、発症する前から、重症度分類の各項目に該当していないかを評価していくことが好ましいと考えられます。
-
Q6SOS治療後のフォローアップにおいて、気を付ける点はありますか?
-
A6
SOSは、治療後に再燃する可能性があることを意識しておく必要があります。
特に、発症リスクが高い患者さんにおいては、一度症状が落ちついた後も油断せず、再燃の徴候がないか慎重な観察を継続していく必要があります。
お役に立ちましたか?
お気に入りメモ